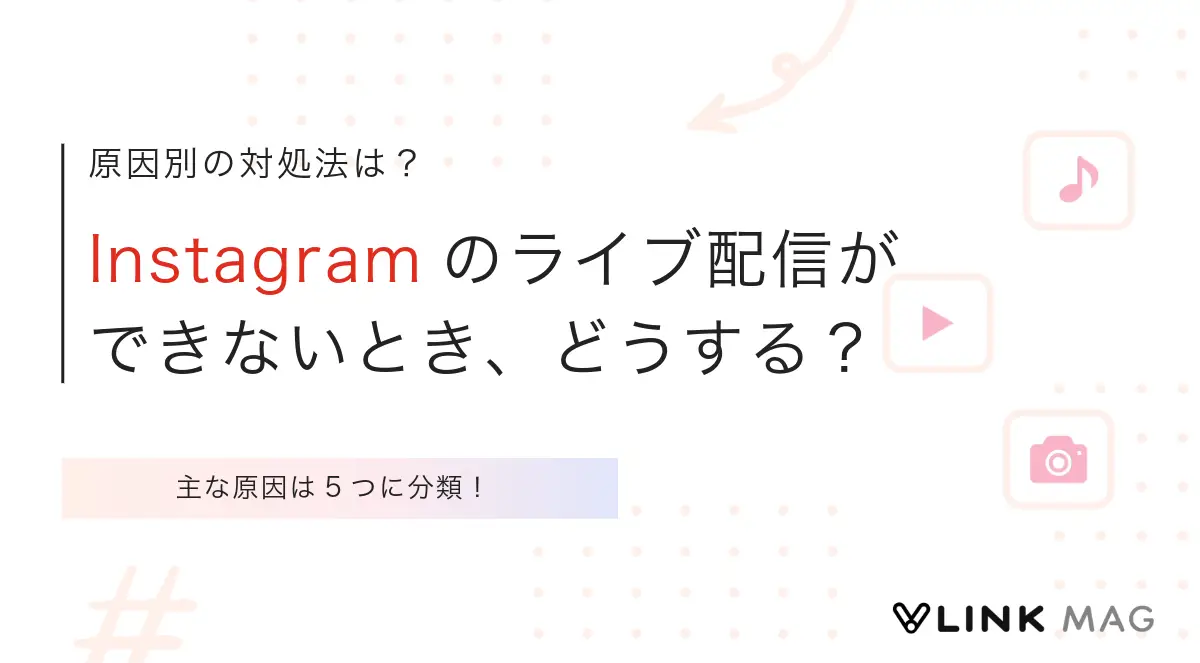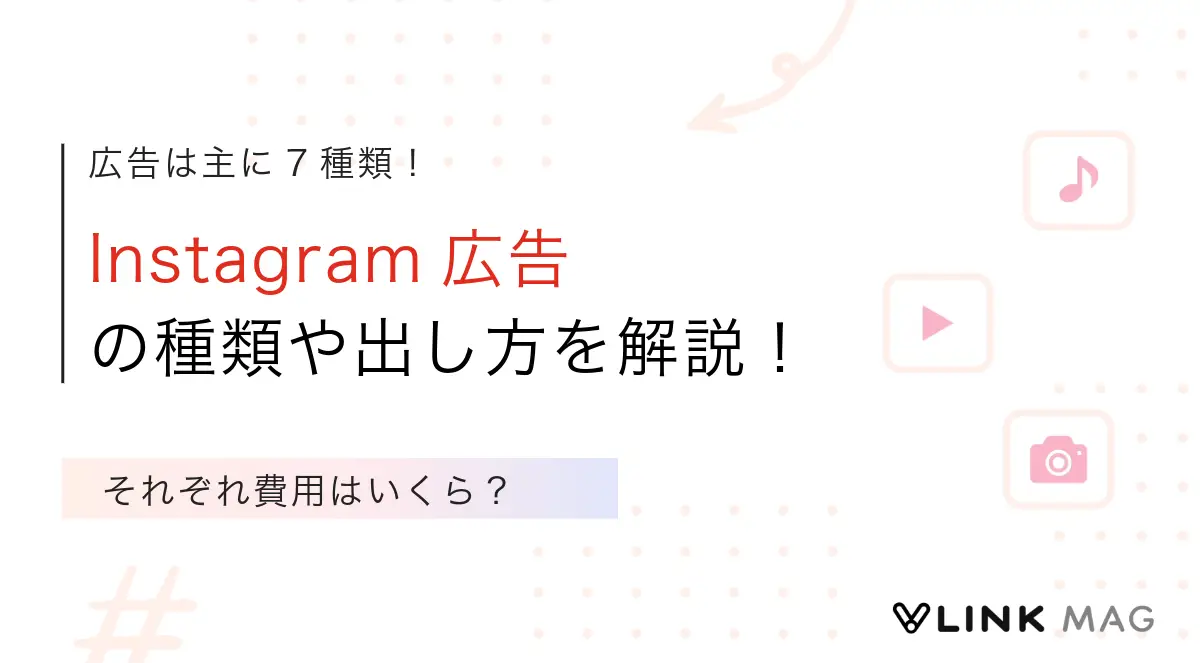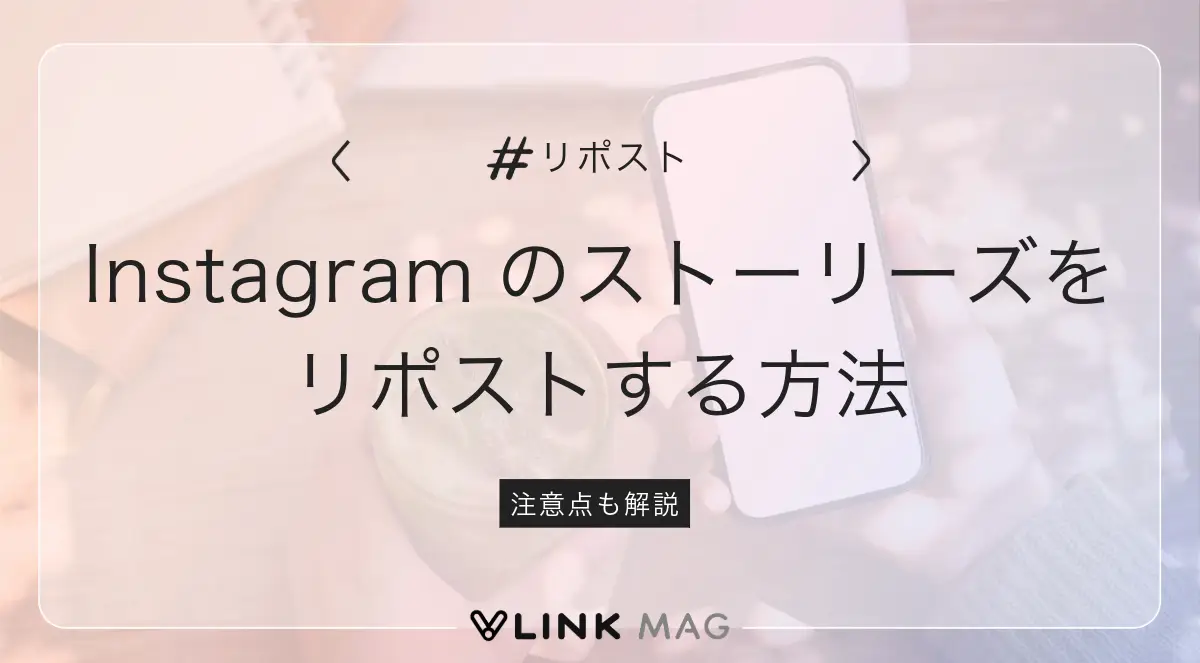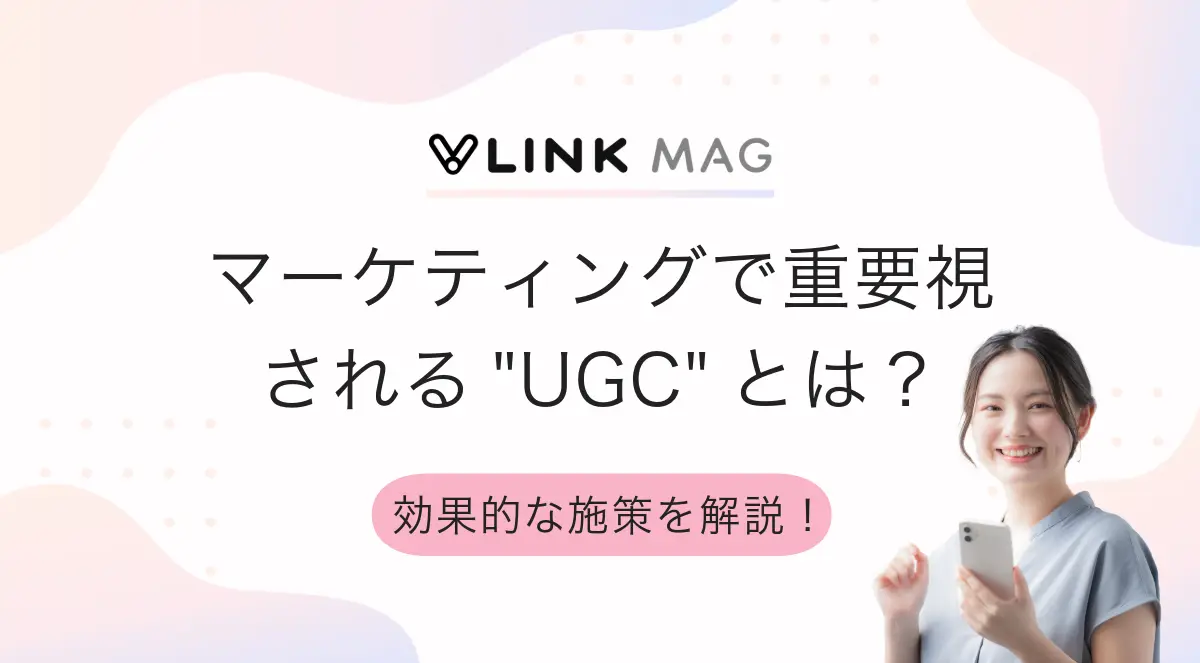
UGCとは?マーケティングで重要視される理由と効果的な施策を解説
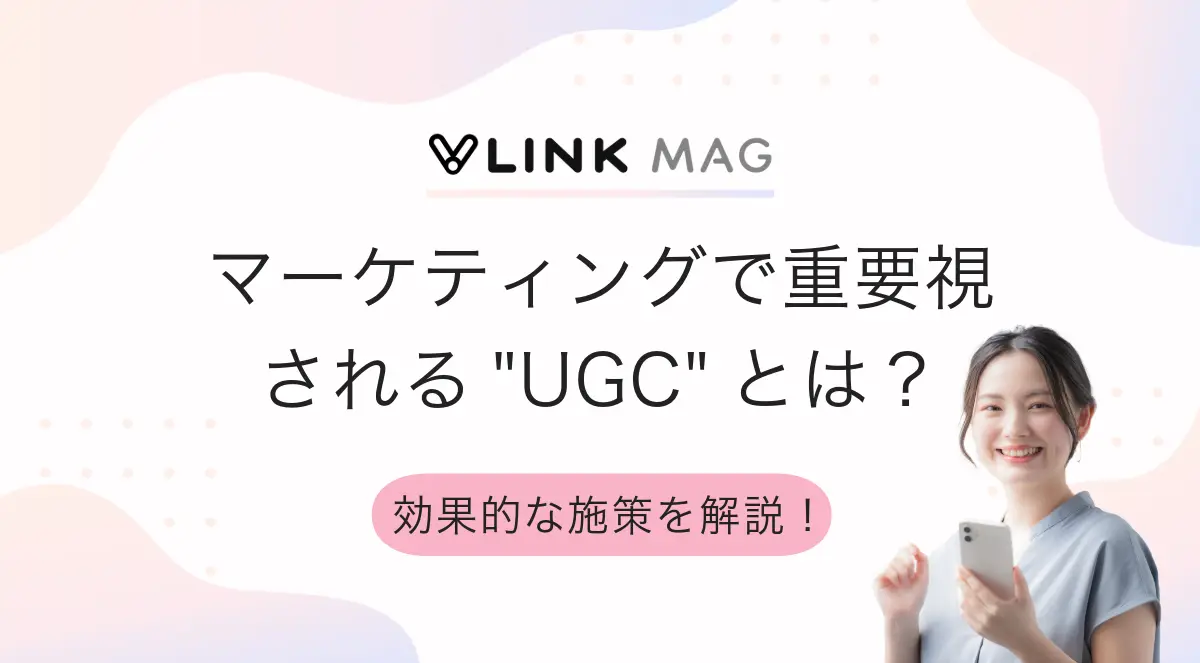
SNSが私たちの生活に深く浸透した今、企業のマーケティング手法も大きく変化しています。その中でも特に注目を集めているのが「UGC」です。消費者が自ら作成・投稿するコンテンツは、企業の広告よりも高い信頼性を獲得し、購買行動に大きな影響を与えるようになりました。
本記事では、UGCの基本的な概念から、UGCを生み出すための施策、注意点まで詳しく解説します。
UGCとは?
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは、企業ではなく消費者自身が作成・発信するコンテンツのことです。例えばSNSに投稿された商品レビューや体験談、ブログ記事、口コミサイトへの書き込みなどがUGCに該当します。
UGCにはリアルな声が反映されるため、消費者からの信頼が高い点が特徴です。企業の一方的な情報発信に比べ、UGCは共感や購買意欲を促進しやすく、ブランドの魅力を多様な視点で伝えられる点も魅力の一つでしょう。
UGCがマーケティングで重要視される背景
UGCがマーケティングで重要視される背景には、消費者の情報収集や購買行動の変化があります。SNSやレビューサイトの普及によって、実際の利用者の声や体験談が購買決定に強い影響を与えるようになったことで、従来の一方的な広告や宣伝では、消費者の心に響きにくくなってきました。
UGCは、企業が発信する情報よりもリアルで信頼性が高いと受け止められやすく、第三者の評価がブランドへの信頼や共感を生み出します。
UGCを生み出す効果的な施策
UGCを戦略的に生み出すためには、ユーザーが自然に参加しやすく、かつブランドの価値観やメッセージを体現できる仕組みづくりが重要です。単に投稿を促すだけではなく、ユーザーが「自分ごと」として楽しみながら発信できる環境を整えることが、質の高いUGC創出の鍵となります。
ここからは、実際に成果を上げている代表的な施策について、具体的に解説します。
ハッシュタグキャンペーン
ハッシュタグキャンペーンは、UGCを促進する代表的な手法です。企業が独自のハッシュタグを設定し、商品やサービスを利用した感想や写真をそのハッシュタグとともに投稿してもらうことで、多くのユーザーが自発的にコンテンツを発信する流れを作れます。
ハッシュタグキャンペーンの強みは、参加のハードルが低く、誰でも気軽に投稿できる点です。優秀な投稿は公式アカウントで紹介するなど、参加者へのインセンティブを用意することで、より多くのUGCを集めることができるでしょう。
公式アカウントでの引用
公式アカウントによるユーザー投稿の引用は、UGCの活性化とブランディングに効果的です。
ユーザーが投稿したコンテンツを企業の公式SNSやWebサイトで紹介することで、投稿者本人の満足度やエンゲージメントが高まります。「自分の声が企業に届いた」という実感を得ることで、ブランドへの愛着や再投稿の動機づけにつながるでしょう。また、第三者のリアルな体験談を企業が認めて発信することで、他の消費者にも安心感や信頼感を与える効果が期待できます。
インフルエンサー施策
インフルエンサー施策とは、影響力のあるインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、その感想を自身のフォロワーに発信してもらう施策です。インフルエンサーの投稿は、一般ユーザーの投稿と比べて拡散力や影響力が大きく、ブランド認知の拡大や新規顧客の獲得に直結しやすいという特徴があります。
ただし、単なる広告色の強い発信ではなく、インフルエンサー自身の言葉や視点を尊重し、自然な形でブランドの魅力を伝えてもらうことが成果を生むポイントとなります。
UGCマーケティングで気を付けること
UGCを活用したマーケティングは多くのメリットをもたらしますが、企業として守るべきルールや配慮すべき点も少なくありません。適切な運用を怠ると、ブランドイメージの毀損や法的リスクにつながる可能性もあります。
ここでは、UGCマーケティングにおいて特に重要な注意点をみていきましょう。
ユーザーの投稿を使う前に必ず許可を取る
UGCを企業の公式アカウントやWebサイトで紹介する際には、必ず投稿者本人の許可を得ることが必要です。ユーザーが自発的に発信した内容であっても、企業が二次利用する場合は著作権や肖像権などの権利が関係してきます。無断で引用や転載を行うと、トラブルや信頼失墜の原因となりかねません。
許可を得る際は、どの媒体でどのように利用するのかを明確に伝え、必要に応じて書面やDMで同意を取得することが望ましいです。
薬機法などの法規制に配慮する
特に医薬品や化粧品、健康食品などを扱う場合、薬機法などの関連法規に注意しましょう。ユーザーの投稿内容がたとえ個人の感想であっても、企業が公式に紹介することで、効能効果を保証するような表現とみなされるリスクがあるためです。
違反が発覚すると、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、企業の信用にも大きなダメージを与えます。UGCを選定・引用する際は法的観点から問題がないかを必ず確認し、必要に応じて専門家のチェックを受けるようにしましょう。
ステルスマーケティング対策を行う
UGCを活用する際には、ステルスマーケティング(ステマ)と誤解されないよう透明性を確保することも不可欠です。企業がインフルエンサーや一般ユーザーに報酬や商品提供を行い、その事実を明示せずに投稿させる行為は、消費者庁のガイドラインに抵触する恐れがあります。
ステマが発覚した場合、企業への信頼は大きく損なわれ、炎上リスクも高まります。UGCを活用する際は、投稿が広告やPRである場合は必ずその旨を明記し、消費者に誤解を与えない運用を徹底しましょう。
UGCをマーケティングに活用しよう
UGCは、現代のマーケティングにおいて企業と消費者をつなぐ役割を果たしています。UGCを積極的に活用し、企業・ブランドへの共感や購買意欲を高めていきましょう。
しかし、UGCの効果を最大限に引き出すには、企業自身のSNSアカウントやプロフィールページの整備が不可欠です。自社の世界観やブランドイメージをしっかりと伝えることで、消費者がUGCを投稿しやすくなり、より多くのファンとつながることができます。
そこでおすすめしたいのが、リンクまとめサービス「VLINK」です。
VLINKを使えば
- 複数のSNSやWebサイトのリンクを1つのページにまとめられる
- 投稿と紹介した商品情報をひもづけできる
- 企業・ブランドの世界観を伝えられる
VLINKで自社だけのオリジナルページを作り、ファンとのつながりを広げてみてはいかがでしょうか。

インフルエンサーマーケティングに役立つ情報を掲載するメディア『VLINK MAG』の編集部です。